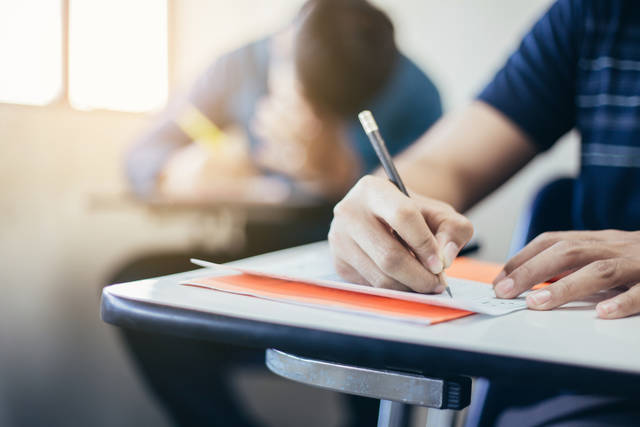バイク車検!一発合格を目指すための抑えるべきポイントと注意点
バイクを所持すると2年ごとに1回、車検を通す必要があります。車検は、それを1度も経験したことがない人にとっては何をすればいいのか、なかなかわからないものです。
また、車検を経験したことがある人でも、2年に1回となると前回の記憶はかなり曖昧になっていて、一発合格できるか不安を抱いているものでしょう。
それらを踏まえて、今回の記事では車検をするにあたって抑えておくべきポイント・注意点を紹介していきます。
また、車検を経験したことがある人でも、2年に1回となると前回の記憶はかなり曖昧になっていて、一発合格できるか不安を抱いているものでしょう。
それらを踏まえて、今回の記事では車検をするにあたって抑えておくべきポイント・注意点を紹介していきます。
バイクの車検はどうすればできる?
バイク、自動車ともに車検の方法は基本的に2種類の方法から選ぶことができます。お金がかかるものの、車検のプロである業者に依頼するディーラー車検と、自分の手で車検をやってしまうユーザー車検の2つです。
ディーラー車検の場合は、車検の依頼にかかる費用と必要書類の用意をしておくだけで、後は業者に任せておけばOKです。
自分でいろいろと整備などをする必要がないので、車検のために大きく時間を割く必要がないというメリットがあります。土日でも請け負ってくれるという点もメリットでしょう。
ユーザー車検の場合は、自分自身の手で、バイクの整備点検をすることになります。ディーラー車検と比べてあまり費用がかからない点がメリットですが、バイクに対してそれなりの知識がなければ成し遂げるのは困難な方法です。
実際に車検を行うとなると、陸運局に持ち込んで車検の手続きを行うことになり、もし車検が通らなかった場合は新しいパーツを買ったり整備をしたりする必要があります。
ディーラー車検の場合は、車検の依頼にかかる費用と必要書類の用意をしておくだけで、後は業者に任せておけばOKです。
自分でいろいろと整備などをする必要がないので、車検のために大きく時間を割く必要がないというメリットがあります。土日でも請け負ってくれるという点もメリットでしょう。
ユーザー車検の場合は、自分自身の手で、バイクの整備点検をすることになります。ディーラー車検と比べてあまり費用がかからない点がメリットですが、バイクに対してそれなりの知識がなければ成し遂げるのは困難な方法です。
実際に車検を行うとなると、陸運局に持ち込んで車検の手続きを行うことになり、もし車検が通らなかった場合は新しいパーツを買ったり整備をしたりする必要があります。
バイク車検にはどれくらいのお金が必要?
バイクの車検には自賠責保険料金、印紙代、証紙代、重量税が必要です。これにプラスして整備代が必要な場合もあります。
また、バイクの車検は自賠責保険に加入していないと受けることができません。自賠責にかかる保険料は、バイクの排気量によって違ってきます。
125cc以下のいわゆる原付は、加入期間12ヶ月で7,500円、24ヶ月で9,950円、36~60ヶ月で12,340円~16,990円が必要です。125cc~250cc以下のバイク(軽2輪)だと、12ヶ月で8,650円、24ヶ月で12,220円、36~60ヶ月で15,720円~22,510円かかります。
250cc超のバイク(小型2輪)は最長契約期間が37ヶ月となり、12ヶ月8,290円、24ヶ月11,520円、37ヶ月で14,950円と他と比べて緩やかに費用が上がっていきます。
重量税は126cc~250ccのバイクだと4,900円必要です。これは届出時にのみ必要となります。
250cc~400ccのバイクは新車登録時に重量税3年分の5,700円が必要となり、以降は登録後12年までは3,800円、13~17年は4,600円、18年以上は5,000円、2年ごとの車検時に重量税として納付が必要です。
国と検査法人に手数料として払うことになる証紙代(自動車審査証紙)、印紙代(自動車検査登録印紙)は、それぞれ1,300円、400円かかります。
(※この保険料は平成29年4月1日以降〜令和2年3月31日以前始期のご契約に適用となります。)
2020年4月1日以降は、125cc以下のいわゆる原付は、加入期間12ヶ月で7,060円、24ヶ月で8,950円、36ヶ月で10,790円かかります。
250cc超のバイク(小型2輪)は、12ヶ月で7,420円、24ヶ月で9,680円、36ヶ月で11,900円かかります。
また、バイクの車検は自賠責保険に加入していないと受けることができません。自賠責にかかる保険料は、バイクの排気量によって違ってきます。
125cc以下のいわゆる原付は、加入期間12ヶ月で7,500円、24ヶ月で9,950円、36~60ヶ月で12,340円~16,990円が必要です。125cc~250cc以下のバイク(軽2輪)だと、12ヶ月で8,650円、24ヶ月で12,220円、36~60ヶ月で15,720円~22,510円かかります。
250cc超のバイク(小型2輪)は最長契約期間が37ヶ月となり、12ヶ月8,290円、24ヶ月11,520円、37ヶ月で14,950円と他と比べて緩やかに費用が上がっていきます。
重量税は126cc~250ccのバイクだと4,900円必要です。これは届出時にのみ必要となります。
250cc~400ccのバイクは新車登録時に重量税3年分の5,700円が必要となり、以降は登録後12年までは3,800円、13~17年は4,600円、18年以上は5,000円、2年ごとの車検時に重量税として納付が必要です。
国と検査法人に手数料として払うことになる証紙代(自動車審査証紙)、印紙代(自動車検査登録印紙)は、それぞれ1,300円、400円かかります。
(※この保険料は平成29年4月1日以降〜令和2年3月31日以前始期のご契約に適用となります。)
2020年4月1日以降は、125cc以下のいわゆる原付は、加入期間12ヶ月で7,060円、24ヶ月で8,950円、36ヶ月で10,790円かかります。
250cc超のバイク(小型2輪)は、12ヶ月で7,420円、24ヶ月で9,680円、36ヶ月で11,900円かかります。
ユーザー車検を申し込む下準備
ユーザー車検をするにあたってはまず陸運局に申し込みをする必要があります。電話、インターネットで申し込めるので余裕を持って予約をしましょう。
予約が成立するとメールで予約番号が送信されてくるので、メモしておくことをおすすめします。
次に必要書類を揃えておく必要があります。車検証自動車納税証明書と自賠責保険証明書、車検証が必要となるので忘れないようにしましょう。納税証明書は役所で再発行も可能なので、もしも紛失してしまった場合は焦らずに役所に向かってください。
これら必要書類のうち、「自賠責保険証明書」は、ユーザー車検当日に現地で入手します。現地に到着したら忘れずに入手しておきましょう。
また、陸運局には見学者用の通路が用意されているので、事前に下見をしておくことをおすすめします。
予約が成立するとメールで予約番号が送信されてくるので、メモしておくことをおすすめします。
次に必要書類を揃えておく必要があります。車検証自動車納税証明書と自賠責保険証明書、車検証が必要となるので忘れないようにしましょう。納税証明書は役所で再発行も可能なので、もしも紛失してしまった場合は焦らずに役所に向かってください。
これら必要書類のうち、「自賠責保険証明書」は、ユーザー車検当日に現地で入手します。現地に到着したら忘れずに入手しておきましょう。
また、陸運局には見学者用の通路が用意されているので、事前に下見をしておくことをおすすめします。
車検前に注意しておくべきポイント
ここで紹介するのは車検の際にチェックされる可能性の高いポイントです。一発合格するためにも、車検に持ち込む前に事前にチェックしておきましょう。
(1)ヘッドライト
テスターを用いて計測するヘッドライトの検査では、光軸と光量をチェックします。バイク車検で行うのはハイビームで100m先をまっすぐに照らすテストです。
基本的な流れは、まずバイクを垂直に立たせて地面からヘッドライトの中心点までの高さを計測し、近くの壁などにその高さの印をつけます。壁などから1mほど離れてさきほど付けた印にハイビームを当てて、その印にハイビームの中心が合っているかを確認します。
バイクを印に向かってまっすぐに立たせて照射させることが大切です。結果がはっきりしない場合はライトのパワーをハイからローへと数回切り替えてみましょう。
以上が光軸のチェック方法ですが、これを目視で判断するのはなかなか難しいです。テストをクリアできるか不安な場合は、事前にバイク屋などで点検、調整などを依頼しておいた方がいいかもしれません。
光量は反射板やライトバルブ、ヘッドライトレンズが過剰に汚れたり、変色したりしていなければ基本的には問題ないでしょう。
ただし、これは2000年以降に販売された車種であればの話です。それ以前の車種の場合、光量が不足している可能性が高いので、バイク屋などの業者にチェックをしてもらっておいた方が無難でしょう。
基本的な流れは、まずバイクを垂直に立たせて地面からヘッドライトの中心点までの高さを計測し、近くの壁などにその高さの印をつけます。壁などから1mほど離れてさきほど付けた印にハイビームを当てて、その印にハイビームの中心が合っているかを確認します。
バイクを印に向かってまっすぐに立たせて照射させることが大切です。結果がはっきりしない場合はライトのパワーをハイからローへと数回切り替えてみましょう。
以上が光軸のチェック方法ですが、これを目視で判断するのはなかなか難しいです。テストをクリアできるか不安な場合は、事前にバイク屋などで点検、調整などを依頼しておいた方がいいかもしれません。
光量は反射板やライトバルブ、ヘッドライトレンズが過剰に汚れたり、変色したりしていなければ基本的には問題ないでしょう。
ただし、これは2000年以降に販売された車種であればの話です。それ以前の車種の場合、光量が不足している可能性が高いので、バイク屋などの業者にチェックをしてもらっておいた方が無難でしょう。
(2)テールランプ・ナンバー灯
テールランプにはフロント・リアブレーキとありますが、これらそれぞれが点灯しないとアウトです。車検に出すバイクが2灯式であるならば両方の点灯が必要となります。
また、LEDによるテールランプの場合、1つでも点灯しない球があると車検をパスできないので注意しましょう。
テールランプと併用されていることも多いナンバー灯のチェックは、ついつい忘れがちなポイントです。特にフェンダーレスキットを取り付けている場合は注意しましょう。
また、LEDによるテールランプの場合、1つでも点灯しない球があると車検をパスできないので注意しましょう。
テールランプと併用されていることも多いナンバー灯のチェックは、ついつい忘れがちなポイントです。特にフェンダーレスキットを取り付けている場合は注意しましょう。
(3)ウインカー・ホーン
カスタムなどを施していなければ、通常動作で問題ないポイントです。カスタムを施している場合は、点滅速度が速すぎたり、ウインカーの大きさや装着している角度が原因での視認面積不足とならないよう注意しましょう。
また、ウインカーでの1番のチェックポイントはウインカーの色です。ウインカーの色はオレンジであることが必須となっているので、ウインカーレンズがクリアカラーの場合はウインカー球自体をオレンジにする必要があります。ホーンは基本的に鳴れば大丈夫です。
また、ウインカーでの1番のチェックポイントはウインカーの色です。ウインカーの色はオレンジであることが必須となっているので、ウインカーレンズがクリアカラーの場合はウインカー球自体をオレンジにする必要があります。ホーンは基本的に鳴れば大丈夫です。
(4)車体寸法
ノーカスタム車であれば基本的には問題のないポイントですが、カスタム車であれば注意が必要となります。ハンドル幅を含む車体の幅が車検証記載寸法の±20mm以内、ミラーを除いての車体の高さが同寸法の±40mm以内、車体の全長が同寸法の±30mm以内に収まらない場合は、構造変更の手続きが別途必要です。
(5)二人乗りの乗車装置
車検証に記載されている乗車定員が2人だと、後部座席、後席用ステップ、後席用のベルト・手すりといったものが必要となります。
(6)排気ガス検査
バイクなどの車両には車体形式というものがありますが、この車体形式に「BC」「EBL」といったものが追記されていると、排気ガスの検査が必要です。
対象車両の場合は、キャブレターの設定、スパークプラグ、エンジンオイルなどの整備に不備がないよう注意しましょう。HC値、Co値などが基準値に満たない可能性があるからです。
対象車両の場合は、キャブレターの設定、スパークプラグ、エンジンオイルなどの整備に不備がないよう注意しましょう。HC値、Co値などが基準値に満たない可能性があるからです。
(7)マフラー
マフラーは比較的なんらかのカスタムを施している可能性の高い箇所です。もしもマフラーの交換などをしている場合は、車検での実測値が基準値から外れないように事前にチェックしておきましょう。
(8)エンジン・タイヤ・チェーン
エンジンがかからないとか走行不能とか、タイヤが明確にひび割れをしているとかスリップサインが出ているとか、チェーンのサビがひどいとか明確に垂れてしまっているとかといった、あからさまな問題が発生していなければこれらは基本的に大丈夫です。
(9)サスペンション
特に注意すべきはオイル漏れです。フロントフォーク、リヤショックは、ともに通常通りに動いていれば大丈夫ですが、オイル漏れは必ずチェックしておきましょう。
(10)ブレーキパッド・ブレーキホース
ブレーキパッドは目視でチェックします。パッドがすり減りすぎてベースプレートとディスクが接触してしまっているような状態でもなければ大丈夫です。ブレーキホースはオイル漏れとホース被膜の痩せに注意します。被膜痩せはホースのカスタムなどをしている場合、特に注意しましょう。
(11)ハンドルロック
ハンドルロックに不備があると、基本的には車検を通すことはできません。簡単に付け外しが可能なものはハンドルロックと認められない可能性が高いので、ボルトなどでしっかりと取り付けておきましょう。またカギは必ず持参する必要があります。
(12)シフトパターンの表示
ミッション車だと、シフトパターンの表示がありますが、この表示文字が剥がれているなどして正しく表示されていないと、車検が通らない可能性があります。そのような場合はマジックなどで書き足したり、シールを貼るなどしてシフトパターンの表示をしておくといいでしょう。
車検を確実に通すためには事前のチェックと知識が大事
2年ごとに必要となるバイク車検。それなりに費用もかかるので出来れば一発で合格したいものです。今回の記事で紹介したポイントをしっかりと抑えて事前にチェックしておけば、一発合格できる可能性は大幅に上がります。
また、ユーザー車検だと費用がぐっと抑えられるのは大きなメリットですが、不安であればディーラー車検を選択するというのも賢い選択でしょう。
また、ユーザー車検だと費用がぐっと抑えられるのは大きなメリットですが、不安であればディーラー車検を選択するというのも賢い選択でしょう。